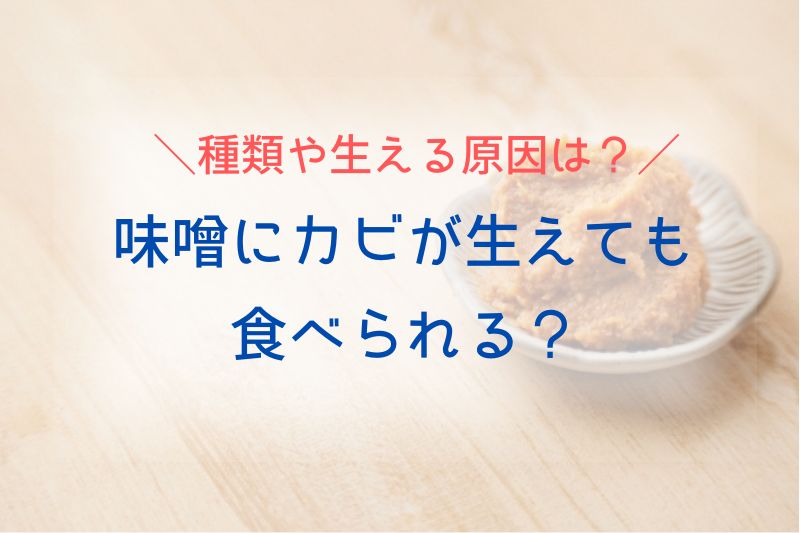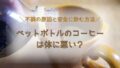私たちの日常生活の中で安心・安全なものを食べるためにも、食品の保存は大切な事ですよね。
しかし丁寧に食品を保存していたつもりが、腐ったり、カビが生えたりとさまざまな問題が起こりますね。
お味噌汁などに普段からよく使う味噌ですが、よくみてみたらカビのようなものが生えていてビックリした!なんて経験をした人もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、味噌にカビが生えても食べられるのか、さらには味噌に生えるカビの種類や原因についてご紹介します!
味噌にカビが生えても食べられる?

味噌にカビが生えた場合、どうしたらいいのかわからないという人もいますよね。
味噌の長期保存によりカビが生えてしまい、食べても大丈夫なのか不安な方も多く、実際のところ処分するというを選択する人も少なくはありません。
ですが、処分はちょっと待ってください!!
結論から言うと味噌はカビが生えても食べる事が出来ます!
「え?」と疑問になる部分を以詳しく解説したいと思います。
「味噌にカビが生えても食べられる?」
まず初めに重要な事をお伝えします。
味噌は市販であっても手作りであってもかなりの確率でカビが生えます。
それはプロが作った味噌でも同じです。
ただし、味噌全体にカビは生えるのではなく、一般的には味噌の表面に生える事が多いです。
そして食べれるのか、食べられないのかは、生えているカビの種類や生えた部分によっても変わります。
味噌に生えるカビの種類や保存方法をちゃんと知れば、カビなんて怖くありません。
なので、カビと味噌の知識を共有しようと思います♪
カビの種類や生える原因とは?

味噌に生えるカビには、白カビ、黒カビ、青カビの3種類のカビが存在します。
それぞれ以下で詳しくご紹介します。
白カビ
この白カビとは、別名で「コウジカビ」と言われ産膜酵母と言う酵母菌の一種です。
カビ=腐ってると思われがちですが、この白カビは、味噌がしっかり熟成されているよ~♪というサインの1つです。
ちょっと不安を煽るような言葉で騙されがちな部分はありますが、人が口にしても全く無害のカビだと言えます。
味噌以外にも醤油や日本酒にも産膜酵母が発生しますが、味噌と違い目に見える事はあまりありません。
なぜかというと醤油や日本酒は、簡単に言えば液体の為、熟成させる為にしっかりかき混ぜます。
ただ、人的には無害でも味噌本来の独特な香りを損なう可能性や品質が落ちる可能性と、次にお話するカビを発生させる関連があるので、発生後はすぐに取り除く必要性はあります。
黒カビ
黒カビという名前を聞くと何となく「黒の方がやばい!?」と感じませんか?
しかし実は黒カビも白カビと似た良い部分を持っているカビです。
黒カビは基本的に味噌を作る段階で見る事の多い黒い物体です。
この黒カビが生えているという事は、味噌が酸化する事でアミノ酸が増え、「味噌がしっかり熟成されましたよ~」という合図です。
味噌は塩分が多く、カビは塩が苦手なので、塩が効いた味噌の上では繁殖しにくいです。
そして、黒カビが繁殖するのは塩分の多い味噌の表面ではなく、実際は白カビの上に繁殖しているという事になります。
そのため白カビも黒カビも無害と言えますが、やはり味噌の劣化を防ぐ為には無害であっても取り除く事が必要とされています。
では、今からご紹介する3種類目の青カビも「無害なのでは?」と思われがちですが、結論から言いますと、こちらは注意が必要なカビなので、以下で詳しくご紹介します。
青カビ
味噌だけでなく、どんな食品でも劣化していく事でカビは生えます。
味噌にこだわらず、さまざまなカビの中でも青カビは比較的毒性は低いですが、実は注意が必要です。
青カビを食べても基本的に害はないと言われていますが、白カビや黒カビと同様に味噌の質を低下させてしまいます。
さらに注意したいのが、青カビはストレスや疲労など免疫力が低下している方が口にすると、食中毒を引き起こす可能性があるという事です。
味噌に含まれる3つのカビを紹介しましたが、1つカビと間違えられやすいものがあるので簡単にご紹介しますね。
それは、味噌を購入する際に見かけた事があるかもしれませんが、味噌に白い結晶のようなものが付着していることがあるのをご存じですか?
これもまたカビに間違われる事もあります。
でも実はこれ、カビではなくチロシンというアミノ酸の一種でカビではありません。
このチロシンは、長期に渡り熟成され麹の力が高い良い味噌と言えます。
カビと似たような姿なので勘違いされやすいですが、カビではありませんのでご安心下さい♪
3種類のカビを紹介しましたが、ほぼ無害という事が判明しました。
ですが、やっぱり出来るだけカビの発生を防ぎたいとは思いますよね。
なので、簡単にカビの発生を防ぐ方法をご紹介します!
味噌にカビが生えるのを防ぐ方法は?

カビが住みやすい環境をご存じでしょうか?
カビは温度20度~30度程度の湿度80%前後の場所を好み住み心地がよく繁殖しやすいとされています。
季節的にはカビにとって、梅雨は最高の時期です。
基本的には味噌も温度の高い場所や直射日光は避けるべきなので、他の食品と同様です。
ただ、味噌を保管する際に重要な事は密閉です。
カビは人間と同じく空気が必要で、日常生活で漂っている空気に食品が触れる事でカビの胞子が付着し、繁殖する可能性が高いと言われています。
そして味噌は発酵が進み、熟成される過程でガスが発生し、固形物と水が上下に分離してしまいます。
すると自然とカビを発生させてしまう原因になります。
なので一番大切なのは、保管時にしっかり密閉し空気を入れない事です。
それでもカビが全く繁殖しない訳ではありませんので、「カビが生えた」と分かった時点で取り除く事が重要になります。
ちなみに取り除き方は超簡単です!
カビには茎や根も存在する為、カビが生えている部分と周辺をスプーンで掘って取る事をオススメします。
そして堀った部分は、またスプーンで平らに戻してあげてくださいね。
これは、窪みを無くす事で分離した際に水を溜めないようにする為です。
その平らにした部分に1つまみ程度、塩をふってあげるとより良いですよ。
後は、とにかく清潔に保つ事。
たったこれだけでOK!!
味噌にカビが生えるのを防ぐ際は、外気に触れる部分をアルコールで除菌したり、味噌に触る時は手を洗ったりと、普段いつも料理する前に行う作業で充分ですので、お伝えした方法を試してみてくださいね♪
味噌にカビが生えても食べられる?カビの種類や生える原因 まとめ
今回は味噌にカビが生えても食べられるのか、そしてカビの種類や生える原因についてご紹介しました。
味噌は長期保存する事が多く、カビが生えると食べられないと勘違いして処分してしまいがちです。
知らないと勿体ない事をしてしまったかもしれませんね。
ただし味噌が長期保存できるといえど、賞味期限等の確認は購入時にしっかりしておきましょう!
今回ご紹介した内容を参考にして頂ければ幸いです♪